じめじめとした梅雨の時期や暑い夏、食中毒のニュースを目にする機会が増えますよね。食中毒は、日常のちょっとした不注意から起こることがあります。
でも、ご安心ください。家庭でできる食中毒予防のポイントを押さえれば、大切な家族を食中毒から守ることができます。
今回は、厚生労働省も推奨する「食中毒予防の3原則」を軸に、具体的な対策をブログ形式で分かりやすくご紹介します。
食中毒予防の3原則とは?
食中毒の主な原因は、食品に付着した細菌やウイルスが増殖し、それを口にすることです。そのため、食中毒を防ぐためには、以下の3つの原則を徹底することが重要です。
- つけない!:細菌やウイルスを食品に付着させない
- ふやさない!:食品に付着した細菌やウイルスを増やさない
- やっつける!:食品や調理器具に付着した細菌やウイルスを殺菌する
この3原則を意識するだけで、食中毒のリスクを大幅に下げることができます。
原則1:つけない!~清潔を保ち、菌の持ち込みを防ぐ~
「食中毒は外から持ち込まれるもの」という意識が大切です。
1. 手洗いを徹底する
食中毒菌は、私たちの手にも付着しています。
調理前はもちろん、生肉や魚、卵を触った後、トイレに行った後、動物を触った後など、こまめに石鹸で手を洗いましょう。
指と指の間、爪の中、手首まで丁寧に洗うことがポイントです。
2. 食材を分けて管理する
肉や魚から出るドリップ(汁)には、多くの細菌が含まれています。
買い物や冷蔵庫での保存時には、ドリップが他の食品に付着しないように、それぞれビニール袋に入れたり、容器に入れたりして分けましょう。
3. 調理器具の使い分けと消毒
生の肉や魚を切った包丁やまな板を、そのまま野菜や調理後の食品に使うのはNGです。
生の食品と、そのまま食べる食品(サラダなど)や調理後の食品は、使う調理器具を分けましょう。
もし難しい場合は、使用するたびに洗浄・消毒(熱湯消毒や漂白剤など)を徹底しましょう。
原則2:ふやさない!~温度管理で菌の増殖を抑える~
多くの食中毒菌は、10℃~60℃の「危険温度帯」で活発に増殖します。
1. 食品は迅速に持ち帰り、すぐに保存
買い物をしたら、寄り道せずにまっすぐ帰りましょう。
特に、冷蔵・冷凍が必要な食品は、最後に買い物カゴに入れ、保冷剤や保冷バッグを活用して温度を保ちましょう。
2. 冷蔵庫・冷凍庫は詰め込みすぎない
冷蔵庫や冷凍庫に食品を詰め込みすぎると、冷気の循環が悪くなり、庫内の温度が上がってしまいます。
目安は7割程度に抑え、適切な温度(冷蔵庫は10℃以下、冷凍庫は-15℃以下)を保ちましょう。
3. 調理後は早めに食べる
調理した食品は、できるだけ早く食べきるのが理想です。
常温で放置すると、菌が急速に増殖する可能性があります。
作り置きをする場合は、粗熱をしっかりとってから、清潔な保存容器に入れて冷蔵庫で保存しましょう。
原則3:やっつける!~加熱で菌を死滅させる~
加熱は、食中毒菌を死滅させる最も効果的な方法です。
1. 十分な加熱を心がける
肉や魚は、中心部までしっかりと火を通しましょう。
加熱の目安は、中心部の温度が75℃で1分間以上です。
特に、鶏肉はカンピロバクター菌、牛肉はO157、魚介類は腸炎ビブリオなど、それぞれ注意すべき菌があります。
2. 電子レンジの活用法
電子レンジで加熱する場合、加熱ムラが生じやすいので注意が必要です。
食材を小さく切ったり、時々かき混ぜたりして、全体に均一に熱が通るように工夫しましょう。
3. 残った食品の温め直し
残ったカレーやシチューなどを温め直す際も、中までしっかり加熱しましょう。
特に、ウェルシュ菌は熱に強い芽胞を形成するため、煮込み料理を大量に作り置きする際は注意が必要です。
もし食中毒になったら…
もし、腹痛、下痢、嘔吐、発熱などの症状が出たら、無理せず医療機関を受診しましょう。
自己判断で下痢止めを飲むと、かえって菌を体内に留めてしまい、症状が長引くことがあるため注意が必要です。
最後に
食中毒予防の3原則
「つけない」「ふやさない」「やっつける」
は、家庭の台所から実践できる大切な習慣です。毎日の料理でこの3つのポイントを意識するだけで、食の安全はぐっと高まります。
このブログが、皆さんの健康で安全な食生活の一助となれば幸いです。

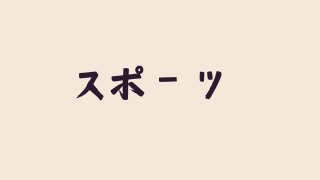
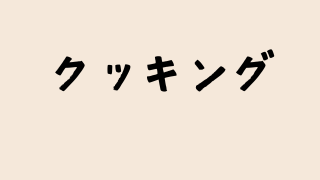
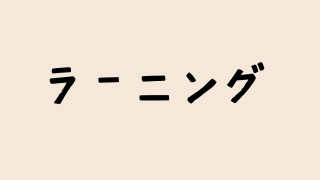
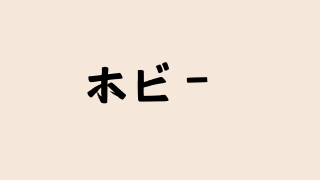


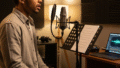
コメント