当ブログを閲覧いただきありがとうございます。
今回は”DOGSO(得点または決定的な得点の機会の阻止)”について解説していきたいと思います。
サッカーを観たりプレイしたりしていて

さっきのはただのファールだったのに
何で今のは一発レッドなんだ???
と感じたことはありませんか?
同じようなファールなのにこの違いは何なのかなぁって。
それはもしかしたら”DOGSO”が適用されてレッドカードが出されたのかもしれません。
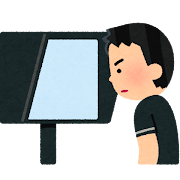
DOGSO
DOGSOとは”得点または決定的な得点の機会の阻止”のことです。
D=Denying(阻止する)
O=Obvious(決定的な)
G=Goal S=Scoring(得点する)
O=Opportunity(機会)
同じようなファールであってもレッドカードが出された場合、
DOGSOが適用された可能性があります。
でも、どのような場合にDOGSOが適用されるのでしょう。
- 反則とゴールとの距離
- 全体的なプレーの方向性
- ボールをキープできる、またはコントロールできる可能性
- 守備側競技者の位置と数
選手がボールに対してチャレンジをした上で反則を犯し、
この4要件を全て満たしたときにDOGSOが適用されます。
1つでもかけた場合はSPA(大きなチャンスとなる攻撃の阻止)として罰せられます。
反則とゴールとの距離
反則を犯した場所とゴールとの距離が近い時に適用されます。
基本的にはペナルティエリア付近、だいたいゴールから25mくらいが目安となりますが、
はっきりとした基準はありません。
ですのでゴールから少し離れた位置でも、その先に守備側DFがおらずキーパーと1:1になるような場面ではDOGSOが適用されることもあります。
全体的なプレーの方向性
全体的な攻撃側選手のプレーが守備側のゴールに向かっているかどうかです。
ポストプレーなどで攻撃側選手がゴールに背を向けていたとすればDOGSOは適用されません。
しかし、一概に選手の向きだけでは判断できず、全体的なプレーの方向性を判断していく必要があります。
ボールをキープできる、またはコントロールできる可能性
その反則がなければボールをキープ・コントロールできたかどうかです。
何らかの攻撃側選手のミス(トラップミス、ドリブルミス等)の場合は適用されません。
守備側競技者の位置と数
守備側競技者の位置と数によって判断します。
基本的にはその反則がければ
キーパーと1:1となる、シュートチャンスになる
あるいはディフェンス側のポジションが崩れている時などに適用されます。
DOGSOで退場にならないケース
退場になるとその試合だけでなくその先何試合か出場できなくなります。
『PK』『退場』『出場停止』の『三重罰』は厳しすぎると言うことで
・ペナルティエリア内でボールをプレーしようと試みて主審がPKを与えた場合
・ペナルティエリア内で意図的でないハンドで主審がPKを与えた場合
に関しては1段階下がって”警告(イエローカード)”となります。
まとめ
今回は、DOGSOについて解説してみました。
ボールをプレーしようと試みて相手の”得点または決定的なチャンスの阻止”
をしたときにレッドカード(退場)となります。
一見するとボールにチャレンジした結果のただのファールに見えるのに、
レッドカードが出たりいろいろとややこしいですよね。
でも、今のファールはただのファールなのか?DOGSOなのか?SPAなのか?
そんなふうにサッカーを観れるとまた観点も変わってきますよ!
さらに詳しく知りたい方は”サッカー競技規則2024/25”に書いてあるので、
ぜひ一読してみてください!
閲覧いただきありがとうございました。

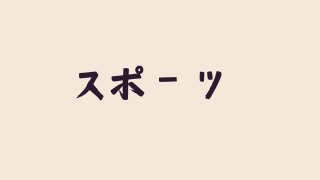
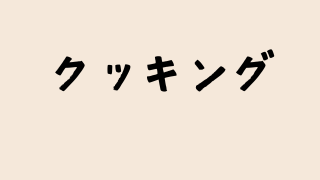
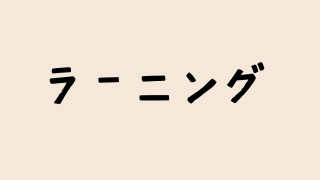
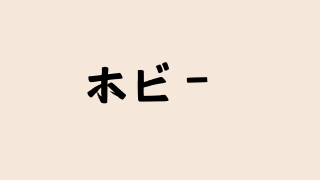
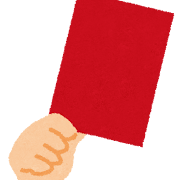
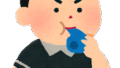

コメント